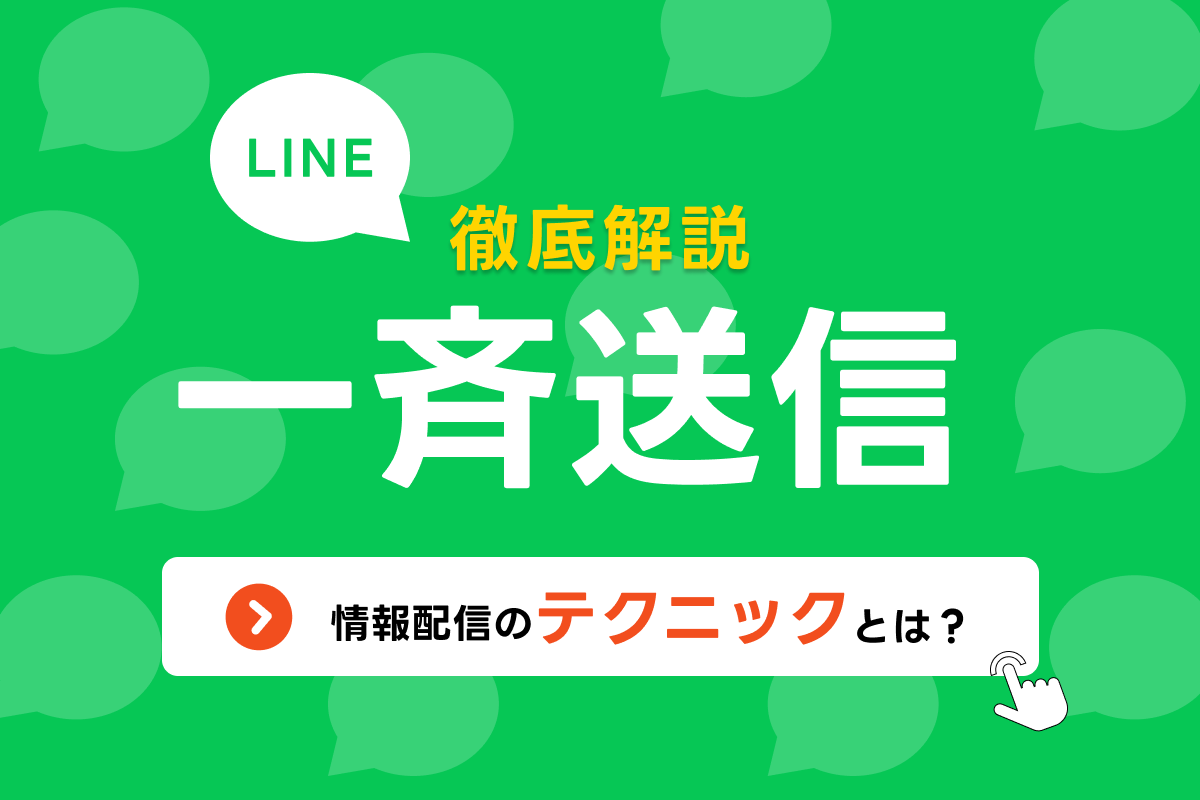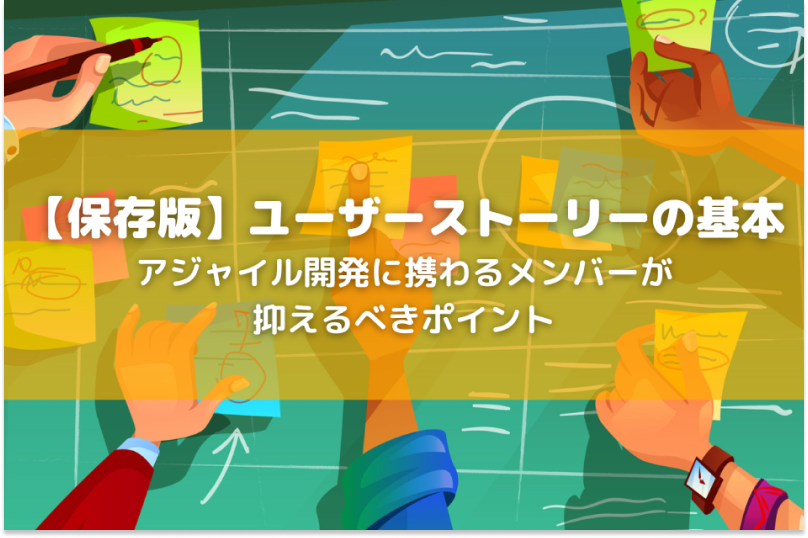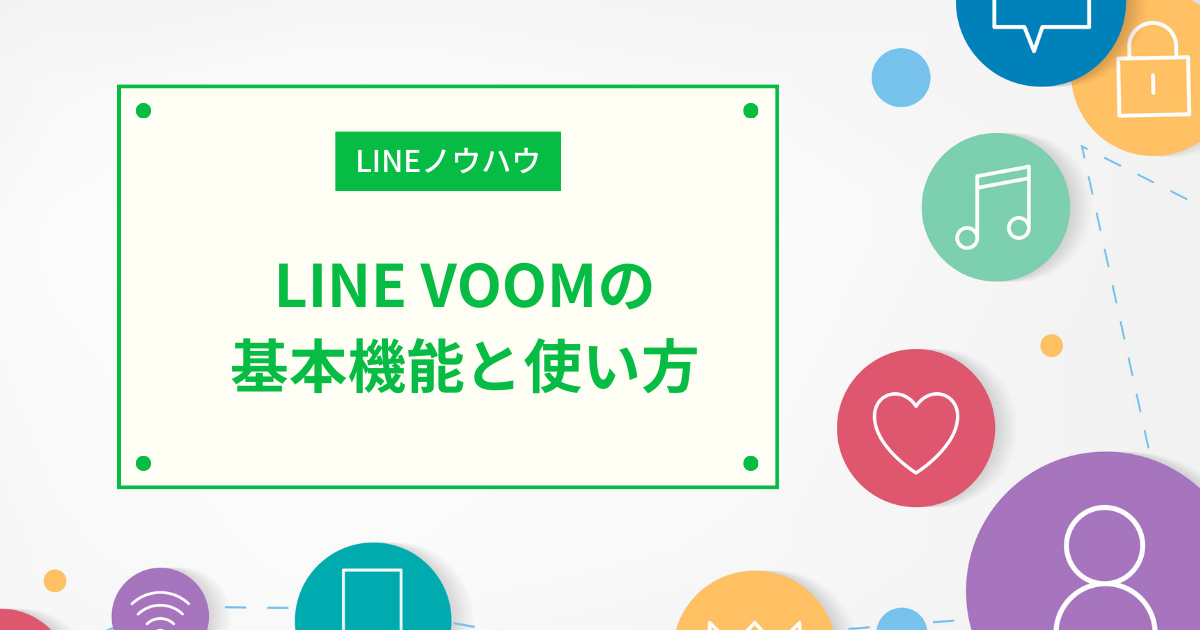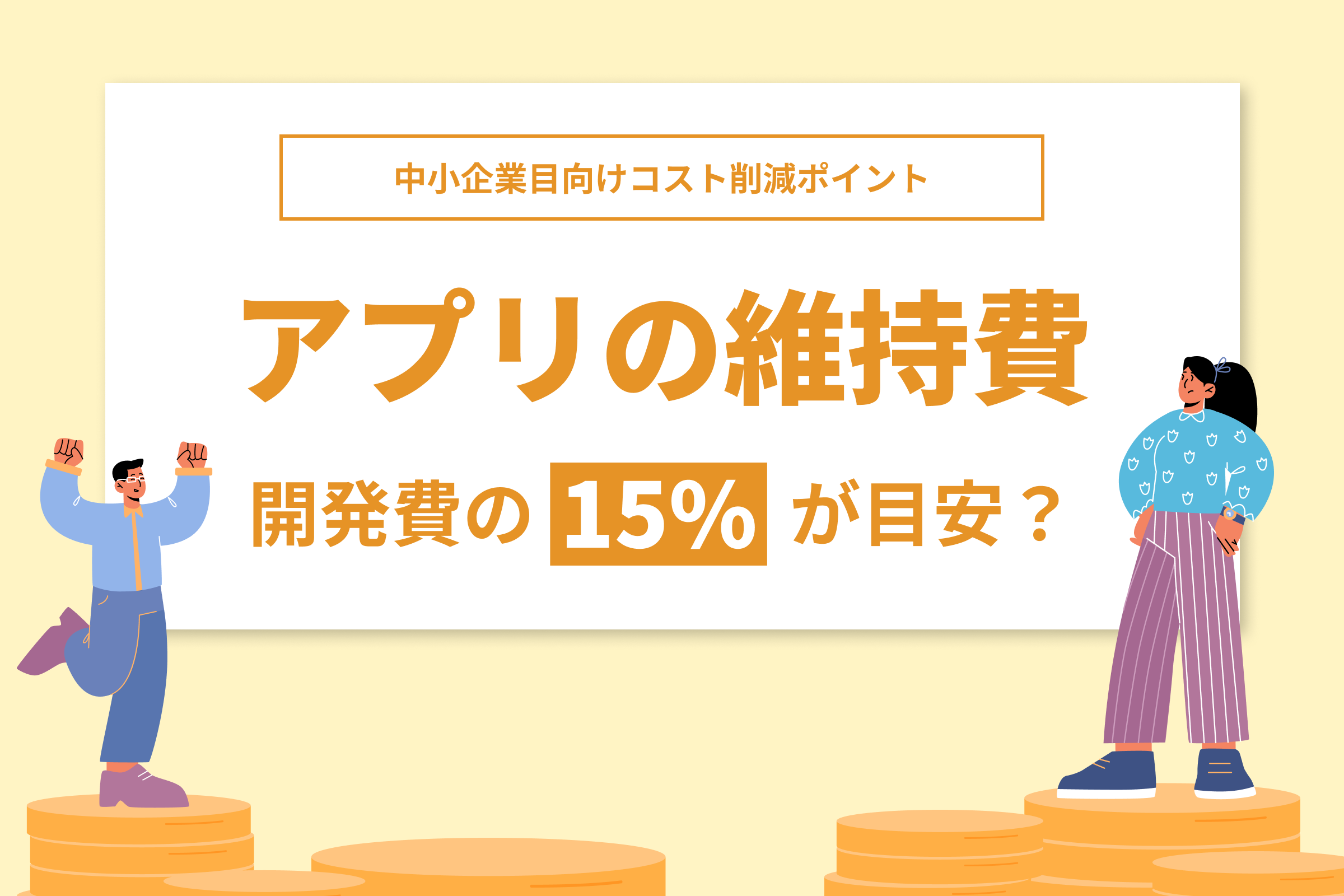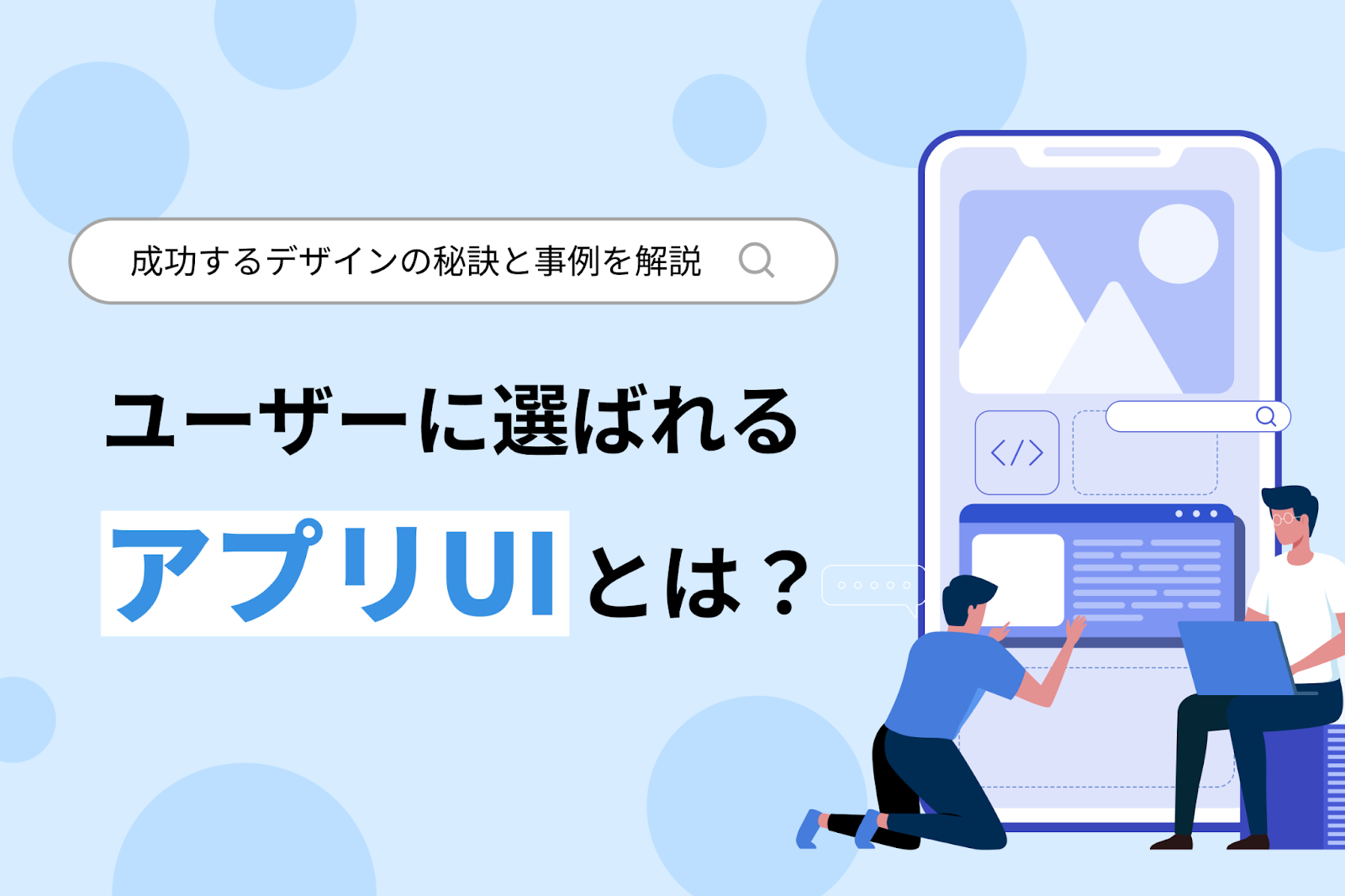
ユーザーに選ばれるアプリUIとは?成功するデザインの秘訣と事例を解説
スマートフォンが生活の一部となった今、アプリの「見た目」や「使いやすさ」は、ユーザーがサービスを継続利用するかどうかを左右する重要な要素となっています。
「良い機能をつくったのに、なぜか使われない」
「ダウンロード数は多いのに、アクティブユーザーが少ない」
このような悩みの背景には、UI(ユーザーインターフェース)の設計に課題があるケースが少なくありません。
本記事ではアプリUIについて、UXとの違いや、ビジネス成果に直結するUIデザインの原則、ユーザーに選ばれるUIのポイントなどを詳しく解説します。
さらに、開発会社として数多くのUI/UX改善に携わってきたEnlytの視点から、国内外の優れたアプリ事例にも触れながら、具体的な改善提案も紹介します。
「アプリの使い勝手を良くしたい」「UIを改善して企業価値を高めたい」とお考えの方に、実践的なヒントをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
アプリUIとは?UXとの違いもわかりやすく解説
UI(ユーザーインターフェース)とは?
UI(ユーザーインターフェース)とは、ユーザーがアプリを操作する際の「見た目」に関する部分です。
スマートフォンアプリであれば、画面デザインやボタン・メニューのレイアウト、文字の大きさ、操作性などがUIに含まれます。UIは「ユーザーとアプリの接点」であり、ユーザーが直感的に操作できるUIが評価されます。
UX(ユーザーエクスペリエンス)との違い
UX(ユーザーエクスペリエンス)とは、アプリを通じて得られる体験全体を指します。
UIとUXの主な違いは以下の通りです。
| UI(ユーザーインターフェース) | UX(ユーザーエクスペリエンス) | |
| 意味 | ユーザーとアプリの接点 | ユーザーがアプリを通じて得る体験 |
| 具体例 | 見た目のデザイン、レイアウト、フォント、ボタンなど | 使いやすさ、満足度、楽しさ、感動、信頼性など |
| 役割 | 情報を分かりやすく伝え、操作しやすくする | ユーザーに「満足した」「楽しかった」と感じてもらう |
| 評価軸 | 直感的か、分かりやすいか、美しいか | 快適か、目的を達成できたか、また使いたいか |
UIは「ユーザーにどう見えるか」、UXは「ユーザーがどう感じるか」と理解するとよいでしょう。
UIとUXは切っても切れない関係にあります。どんなに機能が優れていても、UIが分かりづらければUXは損なわれてしまいます。
つまり、ユーザーに「このアプリをまた使いたい」と思わせる良いUXを提供するためには、分かりやすく使いやすいUI設計が不可欠なのです。
アプリUIがビジネスに与える影響とは?
UIの良し悪しで離脱率が変わる
ユーザーは初回起動から数秒で「このアプリは使いやすいかどうか」を判断します。
例えば、会員登録画面が煩雑だったり、ホーム画面が情報過多で使いにくかったりすると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。アプリのインストール数は多くても、アクティブユーザー数や継続率が低いと悩む企業も多く、背景にはこのようなUI設計の課題があるケースが少なくありません。
特に、購買や予約、問い合わせなどのコンバージョンポイントに至るまでの導線UIでは、直感的に操作できるかどうかが、ユーザーの離脱率を大きく左右します。UIの良し悪しは、ビジネスチャンスを得られるかどうかに直結しているのです。
顧客ロイヤルティとブランディングへの影響
優れたUIは、見た目が良いだけでなく、企業の信頼感を視覚的に表現するブランディング機能を発揮します。
「レイアウトが分かりやすく、快適に操作できる」「欲しい情報がすぐに見つかって助かった」といった体験の積み重ねは、「このサービスをもっと使いたい」「この企業は信頼できる」というユーザー評価に繋がります。
また、アプリを通じたブランド体験が良ければ、ユーザーがその印象をSNSや口コミで広めてくれることもあります。
つまり、UIは広告以上にブランディングするメディアになり得るのです。
良いアプリUIをつくるための3つの原則
一貫性(Consistency)
UIにおける一貫性とは、ボタンの形状や配置、色、フォント、アイコン、余白などのルールを統一し、ユーザーに「予測できる体験」を提供することです。一貫性のないUIは、ユーザーに混乱を与え、操作ミスを誘発する原因になります。
例えば、ある画面では赤いボタンが「削除」、別の画面では赤いボタンが「決定」を意味するようなUIは、直感に反するため混乱を招きます。
UIに一貫性を持たせ、アプリ全体でデザインを統一すれば、ブランドイメージの定着にも繋げられるでしょう。
直感的操作(Intuitive)
直感的なUIとは、ユーザーが初めて使用する際でも「何をどうすればよいか」がすぐに理解できる状態のことです。
ユーザーは普段のスマートフォンの操作や他アプリでの経験から、「このアイコンは戻る」「スワイプすれば更新できる」などの操作性を無意識に期待しています。その期待を裏切るようなUIでは、ユーザーがストレスを感じて、すぐにアプリをアンインストールしてしまう原因にもなりかねません。
このような“慣れ”を意識したUI設計ができていると、チュートリアルなしでもスムーズに操作でき、結果として定着率やCV率が向上します。
視覚的ヒエラルキー(Visual Hierarchy)
視覚的ヒエラルキーとは、「何をどの順番で見せるか」を考慮した情報設計のことです。ユーザーが自然と重要な情報に目を向けられるように、文字サイズや配色、アイコンの大きさ、位置などを意図的に設計する必要があります。
例えば、購入ボタンが目立たない色で画面の隅にあれば、ユーザーは目的を達成できずに離脱してしまうでしょう。CTA(Call To Action)は視線誘導の起点に配置し、ボタンの色やサイズにも明確な意図を持たせるべきです。
良いUIは、ユーザーに「迷わせず、考えさせない」視覚的な導線を提供します。
参考にしたい優れたアプリUIの事例
優れたUIを持つアプリは、ユーザーに快適な利用体験を提供し、サービスの継続利用を促します。使いやすさと心地よさを両立させたUIデザインで支持されている、優れたアプリをいくつか紹介します。
国内アプリの好事例
- メルカリ:多機能ながらも導線が整理されており、初心者でも迷わず使える設計。
- 食べログ:検索機能の導線が分かりやすく、飲食店の情報を比較しやすい。
海外アプリの好事例
- Airbnb:写真を活用したビジュアル訴求と、直感的な検索機能が秀逸。
- Notion:UIカスタマイズの自由度が高い。シンプルでありながら奥深さを兼ね備えている。
Enlytが考える“成果につながる”アプリUI
ユーザー視点 × ビジネス視点の両立
Enlytが目指すUI設計は、「見やすさ」や「使いやすさ」の追求だけに留まりません。
まず取り組むのは、開発依頼主である事業会社と、そのサービスを実際に使うエンドユーザーへの深いヒアリングです。ユーザーインタビューや業務フローの観察などを通じて、ただの要件整理ではなく、事業そのものの課題や提供価値を“再定義”することから始めます。
その上で、UIとは単なる装飾ではなく「価値伝達のインターフェース」であるという視点で、企業のビジョンや強みを視覚的にどう表現すべきかを追求します。
依頼される企業のビジネスを深く理解し、最適なユーザー体験を届けるUIをデザインする。それがEnlytが考える“成果につながる”アプリUIの出発点です。
Enlytの開発スタイル
Enlytの開発スタイルには以下のような強みがあります。
- UI/UX専門チームとエンジニアが連携
- プロトタイピングを通じて、ユーザー行動をシミュレーションしながら開発
- 多言語・多文化対応を想定したUI設計も可能
優れたUIを設計しても、それが開発現場で正しく実装されなければ意味がありません。
Enlytでは、UI/UXデザイナーとエンジニアチームが密に連携し、UI設計を正確に開発要件へと落とし込む橋渡しの役割も担っています。開発プロセスには、プロトタイプによる動作シミュレーションや、技術的制約の洗い出し、さらには運用時の変更にも柔軟に対応できる構成設計まで含まれます。
デザインと開発、そしてクライアントのビジネスの間に立ち、すべての要素が滑らかに連動するよう支援する。それこそが、Enlytが提供する“成果に直結する”UI開発の真髄です。
Enlytの実績紹介
Enlytが手がけたUI/UX開発の代表的な事例を紹介します。
株式会社インターエデュ・ドットコム様「エデュスタ」
「エデュスタ」は、中学受験の学校選びをサポートするマッチングアプリです。EnlytではUI/UX設計から開発までを支援しました。
エデュスタには、偏差値だけでなく校風や特色といった多角的な視点で学校を選びたいというユーザーニーズに応えるため、詳細な検索機能や学校からのスカウト機能を実装。保護者の入力負担を軽減するUI設計にも注力しました。
その結果、アプリリリースから約3ヶ月で目標の3倍となる3万ダウンロードを突破し、新たな学校選びの形を提供しています。
アプリUIの改善や開発でお悩みの方へ
UIの改善からご相談可能です
「既存アプリのUIを見直したい」「初期開発の段階からUIを相談したい」といった声に応え、EnlytではUI改善のみのご相談も受け付けています。
最近、Enlytへのお問い合わせの中で特に増えているのが「やりたいことが多すぎて、開発がなかなか進まない」というご相談です。最初から多数の機能を盛り込もうとすると、開発規模は膨大になり、リリースまでの時間も長くなります。さらに、その機能が本当に必要なのか、ユーザーに求められているのかも検証できていないまま、多額の予算を前提とした構想になってしまっているケースも少なくありません。
このような課題に対してEnlytでは、まずUI設計を通じて本当に必要な機能・デザインを洗い出し、優先順位をつけて「最小構成」での開発からスタートする方法を提案しています。いわゆるスモールスタートで実際にアプリをリリースし、ユーザーの反応やビジネス成果を踏まえた上での段階的な開発を支援します。
UI設計からプロジェクトを始めることは、ビジネスの成功確率を高める第一歩です。Enlytでは「無理のない予算感で開発を始め、確実な改善を積み重ねたい」といったご相談もお待ちしております。
まとめ|アプリUIをビジネスの“資産”にする
アプリUIは、単なるデザイン要素ではなく、ユーザーとの最初の接点であり、ブランド価値を伝える重要な資産です。
優れたUIはユーザーの信頼を生み、コンバージョンやLTVの向上に直結します。一方で、設計が不十分なUIでは、ユーザーの離脱や信頼低下といった大きな機会損失を招きかねません。
だからこそ、UI設計には「誰に、何を、どう伝えるか」という視点と、企業のビジョンや価値を正しく反映するアプローチが必要です。
Enlytは、UI/UX設計をはじめ、事業理解と開発チームとの橋渡しという「実装までの一貫支援」を強みに、ビジネス成果へとつながるUIづくりを支援します。アプリを「ブランド価値を高め、使われるプロダクト」にしたい方は、ぜひ一度Enlytにご相談ください。
UI改善・アプリ開発について相談する