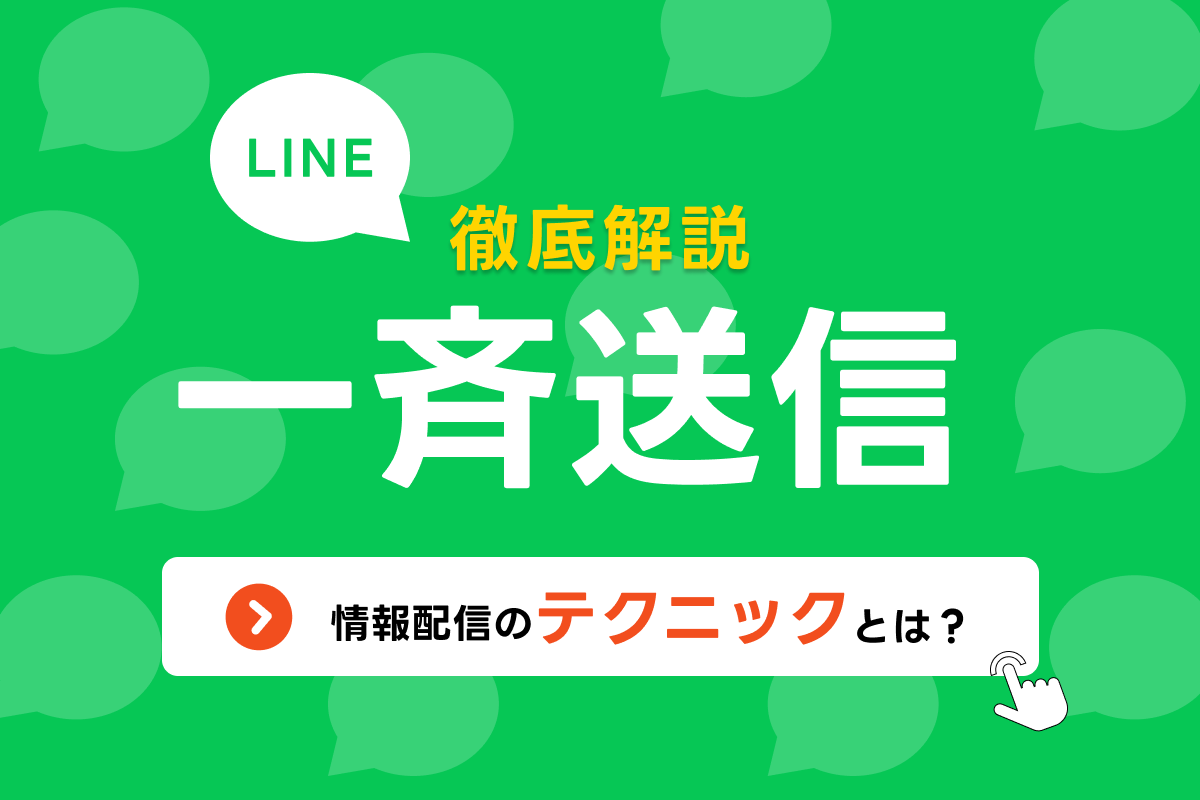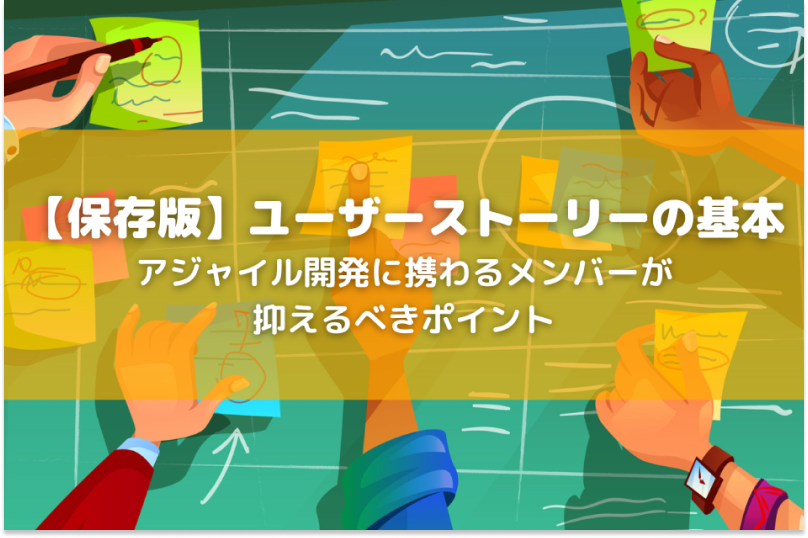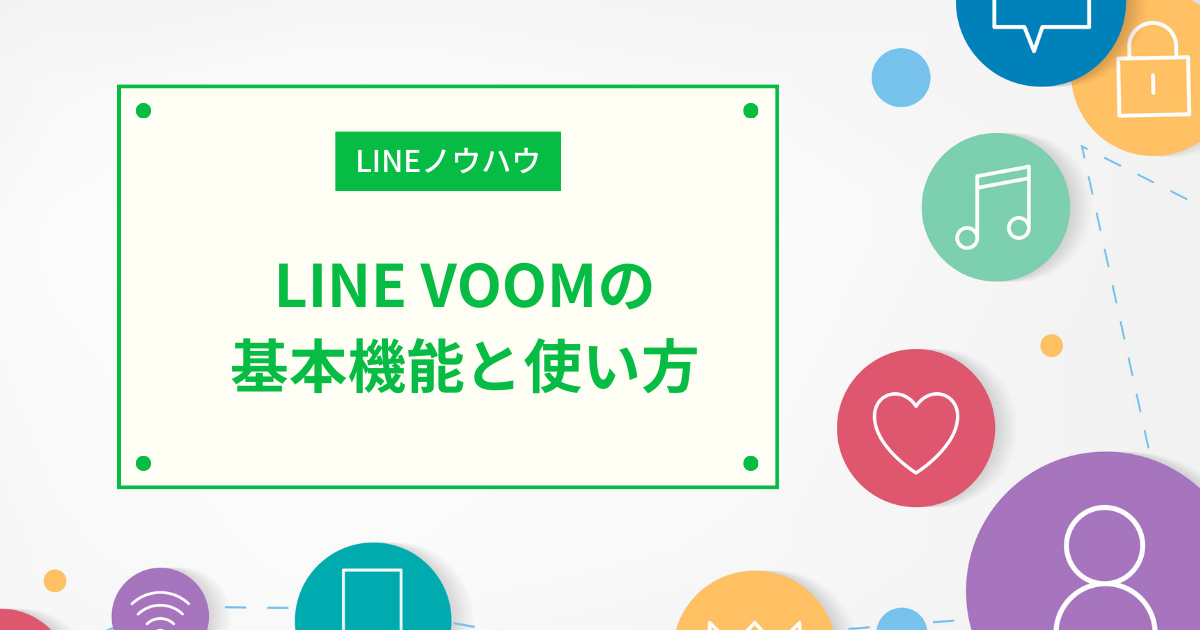飲食店のモバイルオーダーとは?種類やシステム選定前のポイントを解説
スマートフォンの普及とともに、飲食店における注文のデジタル化が急速に進んでいます。特に、新型コロナウイルスの影響をきっかけに、非接触で注文できる「モバイルオーダー」への注目が高まりました。実際、多くの店舗がモバイルオーダーを導入することで、売上アップや業務の効率化を実現しており、今では飲食店経営に欠かせないツールとなっています。
本記事では、モバイルオーダーの基本から導入のメリット・デメリット、そして選定時の重要なポイントまで、詳しく解説していきます。
目次
飲食店のモバイルオーダーとは?
モバイルオーダーは、お客様がスマートフォンやタブレットを使って商品を注文し、決済まで行えるシステムです。従来のレジでの注文や電話予約と異なり、以下のような特徴があります:
- 商品の写真や詳細情報をじっくり確認できる
- 注文履歴の管理や再注文が簡単
- キャッシュレス決済に対応
飲食店におけるモバイルオーダーの種類
テイクアウト向け注文システム
事前に注文と決済を行うことで待ち時間を最小限に抑えられます。
さらに、受け取り時間を指定できるので、利用者は混雑を避けてスムーズに商品を受け取れます。
この仕組みにより、店舗側も混雑を緩和し、効率よく商品を提供できます。
店内向け注文システム
店内に設置されたQRコードを読み取ることで注文が可能となります。
注文は席番号と連携されているので、料理をスムーズに届けられます。
さらに、追加注文も手軽にできるため、スタッフの負担を減らしながら、お客様に快適な食事体験を提供できます。
カスタマイズできるモバイルオーダー
お店の特徴やニーズに合わせて、機能を自由にカスタマイズできます。
既存のPOSシステムとの連携にも対応し、業務の効率化を図ることができます。さらに、オリジナルの画面デザインにも対応することで、ブランドイメージに合った使いやすいシステムを構築できます。
モバイルオーダーが注目されている背景
モバイルオーダーの導入が外食業界で加速しています。
リクルートの2024年調査によると、外食店での注文手段として、テーブルトップオーダー(座席の端末を使った注文)の利用経験率は78.9%、セルフオーダー(QRコードやアプリを活用したスマートフォン注文)の経験率は57.1%、そしてテイクアウト時のモバイルオーダー(スマートフォンでの事前注文・決済)の経験率は48.8%に達しました。特にセルフオーダーは、2021年の26.0%から2024年には57.1%へと大幅に増加し、約2人に1人が利用経験を持つまでに成長しています。
今後も高まる利用意向
今後の利用意向についても、各システムで上昇傾向が見られます。テーブルトップオーダーは72.4%、セルフオーダーは47.6%と、いずれも2021年調査(順に70.1%、42.7%)を上回りました。さらに、テイクアウトでのモバイルオーダーは51.5%が「今後も利用したい」と回答しており、その利便性が広く認知されています。
利用が進む理由は“利便性”
この急速な普及の背景には、消費者の利便性向上が大きく寄与しています。同調査では、セルフオーダーを利用したい理由として、「自分の都合の良いタイミングでオーダーできるから」(51.1%)や「店員を都度呼ぶことに気が引けるときがあるから」(38.5%)が挙げられています。
また、テイクアウト時のモバイルオーダー(スマートフォンでの事前注文や決済)の利用経験率も48.8%と高く、待ち時間の短縮やスムーズな受け取りを求める消費者ニーズに応えています。
これらのデータから、モバイルオーダーは消費者の利便性向上やストレス軽減に寄与し、その結果として利用意向が高まっていることがわかります。飲食店にとっても、注文業務の効率化や人手不足の解消といったメリットが期待できるため、今後さらに導入が進むと考えられます。
参照:リクルート「外食店利用時の注文ツールの利用実態・意向調査」
モバイルオーダーシステム導入によるメリット
人件費の削減
モバイルオーダーシステムを導入すると、注文や会計が自動化され、スタッフの負担が大きく減ります。その結果、ホールスタッフの配置を効率よく行えるため、人件費の節約につながります。さらに、混雑する時間帯でも効率的に対応でき、少人数でもスムーズな運営が可能になります。
売上アップへの効果
モバイルオーダーは、来店したお客様が手軽に注文できるようになり、注文機会の増加が期待できます。
また、システム上でおすすめ商品を目立たせることで、セットメニューやサイドメニューの追加注文を促し、客単価の向上につながります。さらに、顧客データを蓄積し、個々の利用履歴に基づいたプロモーションを行うことで、リピーターの獲得にも寄与します。
オペレーションの改善
モバイルオーダーシステムを導入することで、注文ミスが減り、正確なオーダーができるようになります。
手書きや口頭での伝達ミスがなくなり、厨房への指示もスムーズになります。また、注文データを活用して在庫管理が効率化され、無駄な仕入れを減らして食品ロスを防げます。
さらに、ピークタイムには事前注文を通じて注文が分散され、混雑が緩和されてスムーズな提供が実現します。
顧客分析によるマーケティング効果
顧客の注文履歴や売上データを分析し、販売傾向を把握することができます。このデータをもとに、売れ筋メニューの強化や新メニューの開発など、より効果的なメニュー改善が可能になります。
また、曜日や時間帯に合わせたキャンペーンの実施、特定の顧客層に向けたアプローチなど、効果的なマーケティング戦略にも役立ちます。
モバイルオーダーシステム導入によるデメリット
初期導入コストの課題
モバイルオーダーシステムの導入には、システム構築費や端末購入費などの初期費用に加え、月額利用料やメンテナンス費などの運用コストも発生します。ただ、段階的な導入や必要な機能に絞ることで、初期負担を抑えることも可能です。
スタッフ教育の必要性
新しい操作方法やトラブル対応などをスタッフに教える必要があります。
特にシステムに不慣れな場合、研修期間中はオペレーションがスムーズに進まないことがあります。
そのため、研修マニュアルや操作ガイドを用意し、実践を交えたトレーニングを行うことで、スタッフの不安を軽減できます。また、簡単に操作できるシステムを選ぶことも効果的です。
デジタルに不慣れな顧客への対応
デジタル機器に慣れていない顧客にとっては、操作に戸惑うことがあります。
そのため、店頭でスタッフが使い方をサポートしたり、対面での注文も選べるようにするなど、柔軟な運用が大切です。
導入前に確認!飲食店が知っておくべきモバイルオーダー選定のポイント

モバイルオーダーシステムを選定する際は、自店舗のニーズに合致するかを慎重に見極めることが重要です。以下の視点を押さえながら、最適なシステムを選びましょう。
店舗の特性との適合性
来店する客層や提供するメニューにシステムが対応できるかが、スムーズな運用の鍵を握ります。
例えば、ファミリー層が多い店舗なら直感的な操作ができるUIが重要ですし、ビジネス客が中心であれば、すばやく注文や決済ができるシステムが求められます。
また、カスタマイズ注文の多い店舗では、柔軟なメニュー設定ができるシステムが必要です。
システムの拡張性
導入後の成長を見据え、システムが将来的なニーズに対応できるかを確認しましょう。
機能追加が可能か、POSや会計システムとの連携がスムーズかなど、他システムとの互換性も検討ポイントです。
サポート体制の確認
導入から運用まで安心して利用するために、提供元のサポート内容を把握することが欠かせません。
運用開始後のフォロー体制、さらにはトラブル発生時の対応スピードなどが、運営の安定性に直結します。
コスト面での検討
コストパフォーマンスは、導入を判断するうえで大きなポイントです。初期費用と月額運用コストのバランスはもちろん、決済手数料やアップデート費用などのランニングコストを含めた総合的な費用を比較しましょう。業務効率化や売上向上などの効果も踏まえながら、費用対効果を総合的に判断することも重要です。
これらの視点を踏まえて、自店舗に最適なモバイルオーダーシステムを選定することで、スムーズな導入と長期的な成果が期待できます。
まとめ
モバイルオーダーは、飲食店の業務効率化や売上アップを支える重要なツールです。テイクアウトや店内注文など、用途に合うシステムを選ぶことで、店舗運営をよりスムーズにできます。
導入時は初期費用やスタッフ研修、サポート対応などの課題も考慮が必要ですが、対策を講じれば効果を最大化できます。お店の特徴や成長を見据え、サポート体制やコストを比較検討することが、最適なシステム選びのカギです。
ぜひ、この機会にモバイルオーダー導入を検討してみてはいかがでしょうか。
Enlytについて
Enlytは、ベトナムに開発拠点であるSupremeTechを持ち、50以上のプロジェクトで豊富な実績を積み上げてきました。私たちは、飲食店DXを支援し、店舗のあらゆるニーズに応える柔軟なポイントシステムやモバイルオーダーシステムの構築を提供しています。
自店オリジナルのモバイルオーダーシステム構築で、幅広いソリューションを手掛け、顧客のロイヤリティを高め、ビジネスの収益最大化を一緒に実現します。モバイルオーダーシステムの導入や運用の改善に関心がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。